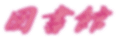 第8回(詩歌特集) ●秦 恒平/著『梁塵秘抄(信仰と愛欲の歌謡)』NHKブックス311 出版年月日1978年 ISBN 4-14-001311-7 梁塵秘抄: 恋ひ恋ひて たまさかに逢ひて寝たる夜の夢はいかが見る さしさしきしと抱くとこそ見れ 閑吟集: 世中(よのなか)は ちろりに過ぎる ちろりちろり 室町小唄: 世中は霰(あられ)よの 笹の葉の上(へ)の さらさらさっと降るよの かつての歌謡がもっていた軽みは現代が完全に忘れてしまった遺物であろう。だれがいま愛の行為(セックス)そのものを再現する「さしさしきし」という、あるいは厳しい時代を受け流す「ちろりちろり」という擬音語を持ち合わせていよう。 ●大手 拓次/著『大手拓次詩集』思潮社 現代詩文庫第II期1010 出版年月日1975年 ISBN 4-7837-0795-2 おそろしく粘着質のある言葉がここに満載されている。 「夜の時」 ちろ そろ ちろそろ そろ そろ そろ そる そる そる ちろちろちろ され され されされされされされ びるびるびるびる びる この大正期の詩人が痴漢だったことを考え合わせて読むといい。 ●草野 心平/著『草野心平詩集』思潮社 現代詩文庫第2期24 出版年月日1981年 ISBN 4783708096 たとえば「春殖」と題して: るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる というだけの詩(図解するとつまらないのですが、蛙のたまごがつらなっているところです)。 たとえば「冬眠」と題して: ● だけの詩。 かれは蛙を「第百階級」と呼んで死ぬまで蛙の詩を書き続けた。たとえば眠る蛙・生殖する蛙・子どもに殺される蛙・考える蛙・ほのぼのする蛙・・・。なんか元気のとても出る詩だよ。 ●金子 光晴/著『金子光晴』ちくま日本文学全集9 出版年月日1991年 ISBN 4480102094 ●金子 光晴/著『金子光晴自伝』講談社文芸文庫 出版年月日1994年 ISBN 4061962817 なにしろ愛する女性に「わたしはあなたのうんこになりたい」とまで歌った詩人である。 だからその反権力の言葉は第二次世界大戦中も凄かったが、かれのそうした性格に死ぬまで影響を与えたのは、アナーキーともユートピアとも言うべき、幼児期!の性体験であったことが、自伝を読むとよくわかるはずだ。 かれの「洗面器」という詩のなかで: 洗面器のなかの さびしい音よ。 と歌われている「音」を、是非とも聴いてみたい気がする(クイズ:洗面器を音を鳴らせているものはなんでしょうか?)。 図書館入り口に戻る |