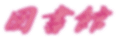 第7回 ●ドストエフスキー,F.M./著、江川 卓/訳『地下室の手記』新潮文庫 出版年月日 1993年 ISBN 4-10-201009-2 かりに世界中が仕合わせになれる真理をだれかが発見したと仮定しよう。だけれど本書の主人公はそんな真理をいとも簡単に破壊してしまう。なぜなら真理などかれにはまったく「関係ない」からだ。 ちょっと専門的に言うとドストエフスキーが攻撃しているのは、当時のロシアに輸入されていたカントの倫理学である。おそらくカント哲学が実現されていれば人類は文字どおり神のような叡知を手にしていただろう。だけれど真理など「関係ない」と言っている個(人)のささやかな思いのほうが、その個にとっては真理よりはるかに大事なのである。 だからこの本を読んでからボクはあらゆる理論を信じなくなってしまった。だとしたら『地下室の手記』はボクをそのかぎりで「不良」にした、ということだけは声を大にして言うことができる。 ●平田 オリザ/著『演劇入門』 講談社現代新書 出版年月日 1998.10 ISBN:4061494228 こんにちはオリザさん。オリザさんのことはテレヴィのニュース・ショーで見て、「あっ、お顔もウーパールーパみたいだし、お話しの仕方もとてもやさしくて、なんかいいひとだなあ」と思っていました。だけどオリザさんの『演劇入門』をぼくは勝手に『外国語学習入門』として読ませていただきました。なぜならオリザさんの書いていることは、 「劇作家」を「外国語教師」、 「俳優」を「学生」というように 置き換えたら、これほど外国語の授業に当てはまる本もないからです。ちょっと較べてみてください、オリザさんの文章をぼく流に書き換えてみました。 オリザさん:俳優とは他人が書いた言葉を、あたかも自分が話すがごとく話さなければならない職業である ぼく:外国語学習者とは外国語で書かれた言葉を、あたかも母語を話すがごとく話さなければならない学習者である こんなふうに『外国語学習入門』として読むという反則技を繰り返しながら、なんども目のうえから鱗がぽろぽろ落ちていったしだいです。 なかでもビックリしたのはオリザさんが発話を、「演説」「談話」「説得・対論」「教授・指導」「対話」「(挨拶)」「会話」「反応・叫び」「独り言」の10カテゴリーに分類して、「日本人は対話の苦手な民族だ」ということを歴史的にも論述していることです。だけれどオリザさんがもっとすごいのは「だったらどうしたらいいのか?」を劇作家として追求していて、このための実践的な秘訣を惜しみなく伝授してくれていることです。 ここからがオリザさんのそれこそ独壇場となっています。ちょっとオリザさんの言っている「コンテクストのずれ」を真似して書いてみます。 1 店長:あの顧客の苦情にはちゃんと迅速に対処したかね? 店員:あのクライアントのクレームはスピーディーにコンシューマー・センターにレポートしておきましたっ! 店長:? (注:たぶん店員は英文卒である) 2 患者:あのー、わたしのー、病状のほうは、それでー、どうなっているんでしょうか? 医師:あなたのようなクランケ(患者)はヘモ(痔)のオペ(手術)のためにまだエントラッセン(退院)できないんですよ。さもないとシュテっちゃう(死ぬ)ほど痛くなっちゃいますよ。 患者:?? (注:ドイツ語は病院の業界語となっている) 3 夫:ちょっと衣紋(えもん)掛け、取ってくれる? 妻:えっ! うちにはエモンカケなんてないわよ。だいいちエモンカケって、なにをカケるもの? 夫:衣紋掛けなんだから、衣紋を掛けるに決まってるじゃないか。 妻:だからエモンってなんなのよ? 夫:だから衣紋だよ衣紋! なんでもいいから服を掛けるの取ってくれればいいんだ! だから服掛けを取ってよ! 妻:だったら最初っから服掛けって言えばいいじゃない! あなただってエモンがなんだか知らなかったくせに。だいたいエモンカケなんてもう言わないの、ハンガーって言うのよ、ハ・ン・ガ・ーって! あなたハンガーも知らないの? 夫:ああ言えばこう言う性格って最悪だね。 妻:あなたのほうこそもっと最悪じゃない、ハンガーのことを服掛けだなんて。あなたも優しかったじゃないの、わたしたちが結婚するまえまでは! (注:「最悪」は最上級だから「もっと」と言うのは文法的に間違いだけれど、こういう場合はいちおう許されてしまう) だからオリザさんは演劇だったら「コンテクストのずれを摺り合わせる」ために: 劇団員として、 1 コンテクストを自在に広げられる俳優 2 わたしに近いコンテクストを持っている俳優 3 非常に不思議なコンテクストを持っている俳優 を採用すると書いています。さらにオリザさんは、 俳優の仕事は、 1 自分のコンテクストの範囲を認識すること 2 目標とするコンテクストの広さの範囲をある程度、明確にすること 3 目標とするコンテクストの広がりに向けて方法論を吟味し、トレーニングを積むこと だとも書いています。この「自分のコンテクスト」を「母語による発話」に、「目標とするコンテクスト」を「外国語による発話」と単純化してしまえば、これはもう外国語学習にもズバリ当てはまる奥義じゃないでしょうか。さらにぼく的に最高に嬉しくなっちゃうのは、オリザさんが「コンテクスト」を「摺り合わせる」「広げる」と言っているからです。なにも「目標とするコンテクスト」に自分を合わせろ、って言っているわけじゃないからなんです! かりにも自分が「自分のコンテクスト」で生きているとすれば、「目標とするコンテクスト」に合わせることは自殺行為もいいところ、さらに言えば「目標とするコンテクスト」へのコンプレックスの裏返しでしかありません。だけれどオリザさんは「コンテクストのずれ」をなくせばいいって言ってるんでもないですよね。だからと言って「自分のコンテクスト」も「目標とするコンテクスト」も絶対化するのではなく、これら自他のコンテクストの「範囲」を「認識」「ある程度、明確に」して「コンテクストを自在に広げる」なんて感動します。この「コンテクストを自在に広げる」ためにも「方法論」を吟味して、ちゃんとそのための「トレーニング」を積む努力もまずはしなさいと。ちょっと見回しただけでももっと始末に負えないケースがありますよね。なるほど「コンテクストを摺り合わせる」と言いながら結局は「自分のコンテクスト」に強引に引きずりこむだけ。あるいは最初から「自分のコンテクスト」に強情に居座るだけでなんにも努力しないとか。 だけれどオリザさんの本は次のような読者にも強力に勧められます。 1 あまりにも仲間内の携帯電話に慣れすぎて異世代とうまく話せない若いひと 2 なんかゼミでうまくコミュニケーションできないとボヤいている学生と先生のすべて 3 これから会社で面接を受けなければならない就職予備軍のひと(必読!) 4 さいきん若いひと(子供・学生)とは話しが通じないなあ、と考えている年取ったひと(親・教員) 5 あまりにも出自が均一化していて上下関係と以心伝心に頼りすぎて困っている組織のひとたち たとえばオリザさんの言っている「プライベート(私的)」な空間を携帯電話空間、「パブリック(公的)」な空間を教室空間として考えるとよく分かるんです。なんで教員も学生もたがいにうまく話せないのかって。おたがいオリザさんの言う意味での「セミパブリック」な空間が欠けているんじゃないかって思うんです。オリザさんは書いていますよね、「会話」とは知り合い同士の楽しいお喋りで、「対話」は他人と交わす新たな情報交換や交流のことだと。だけれど教員側から見ても学生側から見ても、教室内の発話はそれこそ教員から学生への「教授・指導」ばかりになって、ただ情報が一方的にツーっと流れていくだけなんです。だから携帯電話空間に慣れすぎた学生は教室で当てられると、「なんでおれ・わたしが?」という無実の犠牲者のような顔をし、「なにか質問は?」と投げかけたとたんに貝に変身して口を閉じちゃう。ぎゃくに自戒を込めて言いますと教員の側も教室空間は「教授・指導」だけの場だと勘違いして、かたっぱしから学生側からの「会話」を禁じている場面がけっこう見受けられます。たしかに学生の発言はお喋り的な乗りなんだけど授業が面白く展開していく可能性だってあるだけに残念ですね。おたがい「コンテクストを摺り合わせる」ことが出来ないんです。 さらに詳しい奥義は紀伊國屋書店から出ているヴィデオ『平田オリザの文法』でもたっぷり見せていただきました。 きょうはオリザさんからたくさん勉強させてもらいました。 ありがとうオリザさん! 図書館入り口に戻る |