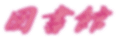 第6回 ●ブコウスキー,チャールズ/著 、都甲幸治/訳『勝手に生きろ!』学研M文庫 ISBN:4059000434 ●ブコウスキー,チャールズ/著 、坂口緑/訳『ポスト・オフィス』幻冬舎 ISBN:4877288295 あらためてブコウスキーの魅力について書いてみたい。ただし今回は趣向をがらっと変えてサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』との比較で書いてみたい。 たとえばボクなんかの世代にとって『ライ麦畑でつかまえて』は、それこそ聖書にも等しいスゴーイ本だった。なんだかんだ言ったって大人って、なんにも分かってないんだよな。この世の中は大人の偽善ばっか満ちあふれているじゃないか。−−おそらく『ライ麦畑でつかまえて』は若い読者に、以上のような同世代感覚をもたらす、「反抗」の書だったと言っていいだろう。だからこそ全世界の多感な若者たちから(共産圏も含む)、あれだけ多くの支持を集めたにちがいない。この主人公ホールデンは大人の社会に打ち負けて、最後は精神病院みたいなところに入っている。あまりに純粋すぎるホールデンが、唯一気持ちを通わせることができるのは、かれ同様に無垢な妹だけだったという点に、サリンジャーの大人嫌いがよく表われている。 おそらくブコウスキーの描くチナスキーの「反抗」と、ホールデンのそれとが決定的に違うのは、ホールデンには入院できる経済的基盤があったのにたいし、チナスキーのほう自分の手で食べて行かねばならなかった点である。たとえば『勝手に生きろ!』は就職課にとっては発禁処分の本である。あいにく正確な数を記録していないけれど(というより記録できないほど多いんだけれど)、たぶん3ページに一回ぐらいの割でチナスキーは失業と転職をしてるのではないか。たしかにホールデンみたいに社会に反抗して討ち死にするのも格好いいけれど、だけど生きているかぎりは当然のことながら食べなきゃいけないんだよ! だとしたら社会の「俗情」と「結託」しないで(日本の純文学版ブコウスキーとも言うべき大西巨人の専売特許)、なおかつ「俗世」で生きていくにはどうするかというのが、ボクの読み取ったブコウスキー文学の最大のメッセージである。 あとはみんながブコウスキーを読んでその答えを見つけてもらいたい。 ●森瑶子/著、『叫ぶ私』集英社文庫 ISBN: 4087493504 これは猪木VSジャイアント馬場などとは、較べものにならない凄まじい格闘技である。ただし闘ってるのは作家の森瑶子と、妻であり母でもある当の森瑶子自身なのだが……。 あるとき森瑶子は自分が我が子を虐待しているのではないかと疑いはじめる。かわいいはずの子どもがどうしても愛せない自分に気付き、フェミニスト・カウンセリングの第一人者、河野貴代美のもとを訪れることになる。これはカウンセリングをその始めから、最終的には中断されるまでの過程を、森瑶子の側が克明に綴った記録である。 だけれど小説家というのはつくづく因果な商売だと思ってしまう。なぜなら人間の心理を描き出すことにかけては、セラピストなど小説家の膝元にも及ばないからだ。だが小説を書くときとはまるでちがって、ここで森瑶子が鋭利な刃(やいば)を向ける相手は、あろうことか他ならぬ自分自身である。かくして自分も母親からは愛されなかった幼児体験や、あるいは夫との不幸な結婚生活+性生活が、これでもかこれでもかというほど剔(えぐ)り出される。あくまでも作家の森瑶子は自分という餌食にサディスティックに立ち回り、ぎゃくに生身の森瑶子はマゾヒスティックに恥部を晒し出す。かような格闘技では言葉はいかなる肉体的な暴力をもいとも簡単に凌駕(りょうが)してしまう。さらに言えばセラピストはここでは闘いを静かに見守る観客でしかない(河野貴代美による「あとがき」はきわめて優れた敗北宣言である)。だが『叫ぶ私』は自分一人で言語のサドマゾを演じている、森瑶子の「人間としての生きる力」が、強力に読みとることのできる闘いでもあるのだ。 なにか自分の生き難さの救いを求めて心理学を勉強してみよう、あわよくばセラピーを自分の仕事にしたいと考える脳天気な人には、きっと頭から冷水を浴びせかける恐ろしい本であろう。およそ常人なら顔を背けたくなる本書の場面に耐えられるなら、そしてそれでも人間の心の奥に立ち入りたいという覚悟のある人だけが、セラピーという仕事に適していると言えるのではないか。こういう意味で本書は一つの試金石たるに相応しい条件を満たしている。 ●河口慧海/著、『チベット旅行記1』講談社学術文庫 263 ISBN: 4061582631 ●河口慧海/著、『チベット旅行記2』講談社学術文庫 264 ISBN: 406158264X ●河口慧海/著、『チベット旅行記3』講談社学術文庫 265 ISBN: 4061582658 ●河口慧海/著、『チベット旅行記4』講談社学術文庫 266 ISBN: 4061582666 ●河口慧海/著、『チベット旅行記5』講談社学術文庫 267 ISBN: 4061582674 たぶんみんなは忘れちゃったんじゃないか。あの猿岩石が世界中を苦労して旅して回ったのを、日本中の視聴者が嘲(あざ)笑いながら+同情しながら、毎週のように手に汗握り見守っていたのを。あのときテレビの画面を見つめていた熱狂とは何だったのか。さらには猿岩石のもたらしてくれた「感動」の賞味期限はどれくらいだったのか(おそらく1年もなかったでしょう:涙)。 きょう紹介する河口慧海さんも猿岩石みたいに、なんの頼る術(すべ)もないのに旅した人である。かれが目指した先は鎖国状態にあったチベットで、なんとこの国に潜入するためにインドで、チベット語をマスターし(外国語の教員として興味津々)、あげくのはてにチベット人になりすまし!、当地の王宮に入るのにまんまと成功し、国王の主治医として何年も平気な顔で仕えていた。おもしろいのは河口慧海さん、なにか困ったことがあると、かならず念仏を唱えるということ。たとえば目の前にどうしても渡れそうにない急流があると、座禅を組むこと数時間して「えいやっ」てな感じで飛び込むと、これが不思議だけれど渡れちゃうんですよねー。なぜ河口慧海さんはこれほどチベットに行きたかったかというと、かれが求めていた仏典がそこにあったからだ。かれは一面で神国日本を背負っていたと言えよう。 かくも大きな目的があると人はたぶん何でも出来てしまう。だから若い人には大きな目的を持ちなさいよ、なんて口が裂けても絶対に言えないけど、そういう目的を持つことが可能な、仕合わせな時代がかつてあった、ということを知るだけでも貴重な本かもしれない。ぎゃくに言えば現代とは可哀想な猿岩石がすぐに忘れられちゃうような可哀想な時代なのかも。きっとテレビで視聴者が猿岩石を見て笑ったり泣いたりしたのは、そこに等身大の自分の姿を見ていたからではないだろうか。 ●サン=テグジュペリ/著、内藤濯/訳『星の王子さま』岩波少年文庫 (001) ISBN: 4001140012 この書評は全世界に何百万もいるファンから袋叩きにあう覚悟で書いてる。なにしろあの『星の王子さま』が相手だから、「なんでわたしの夢を壊すんですか」、「純真な気持ちを汚すとはなにごとか」と読者様の怒りを引き起こすこと必定だろう。だけれどここで勇気を出して書いてしまおう。さらには(特にポストコロニアルをやってるような)研究者も指摘しないので言ってしまおう。 なんでこの本には現地の人が一人も出てこないのか? だって主人公の飛行士はサハラ砂漠に、一人で不時着したんだから当然じゃん、というこれも当然の答えが聞こえてきそうだ。なるほど砂漠に不時着したら現地の人に会えないよね。だけどボクが問題にしたいのはテグジュペリは他の作品でも、おんなじことが言えるってことなんだ。かれは飛行機乗りの自分や同僚のことは、きわめてロマンティックに書く一方で、サハラに住む人々は個々の名前があるはずなのに、「ムーア人」の一言で片付けてしまっている。だとしたらだよ、テグジュペリにとっては、現地の人よりも宇宙人のほうが、身近だった!ということなのか。かくしてサハラの人々は存在感の恐ろしく希薄な舞台装置に貶められる。 あの有名な「砂漠が美しいのは、どこかに井戸があるからだ」という台詞も、テグジュペリの勝手な思いこみじゃないだろうか。たとえば映画『アラビアのロレンス』には、砂漠の井戸にもちゃんと持ち主がいて、所有権をめぐって血生臭い争いが行なわれる、というような場面があったように記憶してるが……。 たしかにボクはモロッコに友達がいるからこんなふうに思うのかもしれないけど、テグジュペリがこんなに素敵な小説が書けたということの背景には、かれがフランスの植民地主義に守られていたという事実は忘れないでね。こんなことを考えながら『星の王子さま』をあらためて読んでください。だけど(それでも)世界中のテグジュペリ・ファンからやっぱり袋叩きにあうんだろうなー。 図書館入り口に戻る |