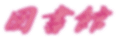 第2回 ●ヘロドトス/著、松平 千秋/訳 『歴史・上』 岩波書店 ISBN 4-00-334051-5 ●ヘロドトス/著、松平 千秋/訳 『歴史・上』 岩波書店 ISBN 4-00-334052-3 ●ヘロドトス/著、松平 千秋/訳 『歴史・上』 岩波書店 ISBN 4-00-334053-1 きっと世界史でヘロドトスは「歴史の父」ということを習ったかも知れないが、かれを「歴史の父」として読むのはあまりに勿体ない話しだ。 ちょっとだけ例をアトランダムに挙げてみよう。 巻一、8 カンダウレスは自分が溺愛する妻の美しさを自慢するため、ギュゲスという部下に妻の一糸纏わぬ姿を覗き見(!)するよう命令する。 巻八、104 ヘロドトスの故郷に近いペサダでは災厄が迫ると、なんとこの町の巫女たちの顎から長い髭が(!)生えてくる。 巻二、46 エジプト人の女は雄山羊と公然と交わっている(!)。 巻七、35 ペルシャ側のクセルクセスはギリシャ遠征の途中で、ヘレスポントスという海峡に橋を掛けようとする。だけれど嵐のため架橋に失敗したことに怒ってヘレスポントスを「鞭打ちの刑」(!)にする。かれは怒りのあまり海峡そのものを懲らしめるのだ。 巻二、1 エジプトのプサンメティコス王は人類最古の民族が知りたかった。だから生まれたての赤ん坊を隔離して言葉をいっさい聞かせないよう命じた。なんの言葉を学ばなかったにもかかわらず、この赤ん坊が最初に発したのが「ベコス」というプリュギア語だったので、プサンメティコス王もエジプトが最古の民族だという主張を撤回した。 巻二、111 またもやエジプト王のことだが失明したペロスは、ヘリオスの神殿にお伺いを立てたところ、「夫だけにしか交わったことがなく、他の男を知らぬ女の尿(!)で眼を洗えば、ふたたび目が見えるようになる」との託宣がくだった。さっそく自分の妻で試みたが一向に回復せずに(笑い!)次から次へと多くの女を試みていった。さて遂に目が見えるようになったかれは、これまで試みて失敗した女(むろん妻も!)をある町に集めてみんな焼き殺してしまい、たった一人だけ目を治してくれた女を自分の后に入れたのである。 巻三、101 インド人たちの精液は膚の色とおなじで黒い色(!)をしている。 巻六、107 ペルシャ軍をマラトスへ誘導したヒッピアスは、なにぶん高齢だったので烈しいくしゃみに襲われたとき、この勢いで一本の歯が抜けて口から飛び出してしまった(笑い!)。 これだけ挙げればもう『歴史』が!や?や笑いが満載だってことは分かるだろう。なんて言ったってヘロドトスは「歴史の父」であるよりは「トンデモ本の父」なのである。だけれど早合点しちゃいけないんだけどヘロドトスは自分が旅しながら見聞きしたことしか書いていない。さらに注意しなければならないのはヘロドトスの書いていることは、かなりの部分が人類学などの研究から支持されはじめている点である。ことの真偽についてはぼくも正直言ってさほど関心がないのだが、これだけのことを自分の足で歩いて書き集めたヘロドトスには烈しく嫉妬してしまう。だってかれはインドやスキタイから現在のモロッコまでをカバーしているんだから。かれは旅行ガイドも語学学校もない時代に一人でどうやって旅していたのだろう。あの「恐れ入谷の鬼子母神」のとはこのことである。なんかすごくえらいぞっ、ヘロドトス、ってつい応援したくなっちゃうじゃないか。 だがヘロドトスの恐るべき点はこれだけに尽きるわけでない。かれが『歴史』を書くに至った理由はギリシャ人とペルシャ人との戦争を究めるということだったのだが、あくまでもギリシャ側の一員だったにもかかわらずヘロドトスは必ずしもギリシャびいきではない。このあたりは実際に『歴史』を手にとってペルシャ側をめぐる記述を読んでもらうしかない。たとえばギリシャとペルシャとの戦争と言うと最近のオリエンタリズム論をつい想像してしまうのだが、かれにはギリシャを持ち上げる姿勢が微塵も見られないのはどういうわけなのか。 だからヘロドトスは二千年前の男なのにぼくにとっては読めば読むほど興味の湧き起こってくるライバルなのだ。 図書館入り口に戻る |